 |
| 逆ウォッチ曲線は、ある銘柄が現在、相場サイクルのなかでどのレベルにあるのかを折れ線グラフによって一目で見られるように工夫されたものです。株価と出来高の関係から相場を予想しようとするもので、出来高の概念をそのまま折れ線グラフ化しています。 |
| ■逆ウォッチ 逆ウォッチの描き方は、株価を縦軸に出来高を横軸にとって、ラインを引いていくものです。日々の株価の動きが荒すぎるとラインが細かく複雑になって、何だかわからなくなりかねません。そこで株価と出来高をともに移動平均化することによって、ラインを滑らかにします。一般的なパラメーター(指数を調整する数値)としては25日を利用します。 逆ウォッチ曲線は、相場における出来高と値動きの関係を示すものですが、実際の売買においては、買い場が近いのか、それとも売り場が近いのかを判断するのに役立つものと言われています。出来高の増加は株価上昇の動きを伴うという特徴がありまますから、これまで売りの局面だった相場でも、ようやく出来高が増加し始めると、逆ウォッチ曲線のチャートは右に移動し始めます。それが株価の上昇を伴うようになれば、買いのシグナルと捉えるわけです。オシレーターなどと併用して、実際の買いタイミングはそちらに頼るなどの工夫で精度は一段向上します。 具体的に、縦軸を株価、横軸を出来高とすると、株価が上昇してから下落するまでの一連のサイクルは、図のように8つの段階に分けて説明できます。 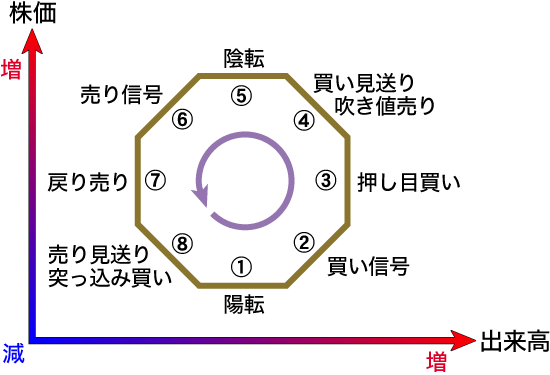 1.株価はまだ低位にあるが、出来高が増加しはじめる。陽転の兆しと見て買い場を探る。 2.出来高が増えて、株価も上昇している。買い信号と見て、買い行動に入る。 3.株価はなおも上昇するが、出来高は変わらない。押し目があれば買う。 4.株価上昇の勢いが鈍り、出来高も減少し始める。この時期では買いは見送り、吹き値があれば売り抜ける。 5.株価の上昇が止まり、出来高は減少し続ける。陰転の兆しと見て売り場を探る。 6.なおも出来高が減少し、株価も下降し始める。売り信号と見て、売り行動に入る。 7.出来高が低調で、株価も下げている。戻り場面があればすかさず売る。 8.株価は下げ続けるが、出来高に回復の兆しが見える。売りを手控え、下げ過ぎがあれば買う。 このように1から8までのサイクルは、図で見ると時計と逆方向に回るということが、逆ウォッチ曲線の名称の由来となっています。移動平均値のなだらかな線で描きますが、理論どおりのきれいな8角形になるのは極めてまれです。 |